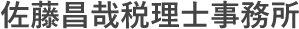法人 不動産 売却 税金 計算
- 法人が不動産を売却した時にかかる税金と計算方法
個人が不動産を売却した場合には、譲渡所得税が課税されます。一方、法人が不動産を売却した時には、他の所得と合算して法人税などが課税されます。今回は、法人が不動産を売却した時にかかる税金と計算方法について紹介します。法人が不動産売却をした時にかかる税金法人が不動産を売却した時に課税される可能性がある税金は、以下の5
- 個人事業主・フリーランスの税金対策について
そしてこれを踏まえて税金が課せられることになります。個人事業主・フリーランスが支払う必要がある税金は、所得税・住民税・事業税・消費税の4つです。 ①所得税所得に対して課される税金になります。 ②住民税これも所得を踏まえて自治体から通知が来たときに納税をする必要があります。 ③事業税これは業種により税率が異なり、事...
- 税務申告の流れ
企業などの法人が確定申告をしなければならない税金は、法人税・法人住民税・法人事業税・消費税・固定資産税などです。これらの税金は事業年度終了の翌日から2ヶ月以内に申告しなければなりません(申告期限の猶予がある税金もあります)。 税務申告をするためには、まず決算を経る必要があります。決算書の作成時期は事業年度終了の3...
- 税務業務とは
具体的には、①税務代理、②税務書類の作成、③税務相談、④税金対策の4つが挙げられます。 ①税務代理税務代理とは,納税者本人に代理して税務署に対して税金の申告や申請を行ったり,税務署からの調査や処分に関して税務署に対して納税者本人に代わり主張・陳述をすることをいいます(税理士法2条1項1号)。原則として納税申告や申...
- 経理業務の目的と流れ
まず、決算整理を行い、利益を確定、そして税金の計算を行い、確定申告書を作成します。その後、税の仕訳を入力し、決算書の作成を行います。他にも、法人の場合、社員の社会保険加入は義務付けられて落ち、加入手続きを経理が行うことが多いです。 佐藤昌哉税理士事務所は、名古屋市・北名古屋市・春日井市・東海市・瀬戸市を中心に、愛...
- 【売り手・買い手別】M&Aの目的やメリット・デメリット
とは、事業を第三者の法人等に売却して、事業を他社と合併させることをいいます。このM&Aは、親族内承継や会社内承継と異なり、売却をすることによって事業承継を行うパターンですが、この目的やメリット、デメリットはどのようなものがあるのでしょうか。以下で詳しく見ていきましょう。M&Aの目的とM&Aで税理士ができることM&...
- 法人税の繰越欠損金|適用できる条件や期間は?
法人は、利益に対して法人税の納税が義務付けられています。法人税は益金から損金を差し引いた金額に対して課せられる税金です。損金の方が大きい、つまり一般的な言い方をすれば赤字経営の場合、法人税はかからないということになります。黒字の場合には、経費などを差し引いた課税所得に対して法人税がかかります。法人の益金よりも損金...
- 赤字でも確定申告するメリット・デメリット
確定申告とは、1月1日から12月31日までの1年間の所得を税務署に申告し、所得税を計算して納税する手続きのことです。申告と納税は、毎年2月16日から3月15日までの間に行う必要があります。確定申告を行う必要のある方は、基本的に個人事業主やフリーランスの方です。会社員の場合、年末調整が行われるため基本的に確定申告が...
- 株式譲渡による事業承継の具体的な方法を解説
また、相続時精算課税制度や事業承継税制などの制度を利用することによって、事業承継時に支払う税金を低くできたり、猶予できたりします。事業承継税制を利用している場合、贈与者である先代経営者が亡くなると、適用を受けた株式は、後継者にあたる相続人が、相続、または遺贈によって取得した財産となり、他の相続財産と一緒に相続税を...
- 銀行対策や資金繰り問題を税理士に相談するメリット
また、新設法人の場合には決算書がないために事業計画書などで審査をすることになります。また、会社で融資を受けた場合には返済をすることになりますが、ここで会社の資金繰りが悪化しているなどで返済が出来なくなったということは一番避けたいことです。 ここで、税理士をご活用いただくことによって、銀行の融資対策や資金繰り問題を...
- 税務のアドバイスを税理士を受けるメリット
税制法は、所得税や消費税、法人税などの各種の税を総称した複合的法制度といえるわけですが、税金が我々の生活にかなり密接に関わっているにも関わらず、税に関する諸法律は煩雑で、わかりにくいものです。その上、改正頻度も比較的多く、一般人にとっては馴染無ことが難しい法制度であるといえます。税理士のアドバイスにより専門知識を...
- 税務調査の対応について
もし納税者による違法・脱法行為が発見された場合にはしっかりと税金を納めさせることはもちろん、追徴課税が課されることもあります。納税の義務がある以上逃れることはできないものです。 税務調査は基本的に電話で事前に連絡されることが一般的です。この際の対応としては、税理士がいる場合には税理士に代わる、税理士がいない場合に...
- 追徴課税のデメリット
追徴課税(附帯税)とは、納付期限までに所定の税額を完納していなかったり、納付期限までに納税をしていない場合に生ずるペナルティー的な税金のことです。例えば、法人税は、法人決算を行なったとき(決算日である12月31日または3月31日)から2ヶ月以内に申告をするとともに納付をしなければなりません。この期限内に法人税を納...
- 確定申告しないとどうなるのか?無申告のデメリット
原則として、納付すべき税額に対して、50万円までは15%、50万円を超える部分は20%の割合を乗じて計算した金額を支払う必要があります。ただし、法定期限から1ヶ月以内に自主的に納税をし、これまでに確定申告を怠ったことがない場合には無申告加算税を支払う必要がありません。 また、申告で確定した税額を納付期限内までに完...
- 経理業務・会計支援業務を税理士に依頼するメリット
経理業務とは、売上管理、仕入れ管理、給与や保険の管理、税金の計算など、会社のお金の管理に関する業務のことを指します。会計業務とは、会社の年間売上と、支出を計算し、その差額から算出される利益に税率をかけ、納めなればならない納税額の計算、今後の経営、事業に必要となるお金の額の計算を行うことを指します。 これらの業務は...
- 法人の節税方法とは
そこで、以下では法人の節税方法をご紹介します。 ■経費の見直し経費として処理できるにもかかわらず、経費として扱わず、自己負担している場合、それらを経費として計上することで、節税に繋がります。中小企業向けの共済も経費として計上することができます。共済とは、従業員の退職金の準備や、事業が悪化した際に、無利子での貸付が...
- 資金繰り表の作り方
具体的には、「借入」、「資産の売却」、「支払いの先延ばし」の3つがあります。 ■資金繰り表の作成法資金繰り表は次の順番で作ります。 ①売上代金の回収予定を資金繰り表に計上する。②その他入金予定を資金繰り表に計上する。③仕入代金・材料費・外注費の支払い予定を資金繰り表に計上する。④人件費支払い予定を資金繰り表に計上...
- 役員報酬で節税することは可能?押さえておくべきポイントとは
■役員報酬と法人税法人税は会社の利益に対して課税されます。そのため、役員報酬をあげることによって法人税の課税対象から役員報酬分が給与として差し引かれるため、役員報酬を高めることで法人税の節税を行うことが可能です。しかし、役員報酬をあげることで同時に社会保険料があがってしまい、その分会社の負担も大きくなってしまいま...
- 相続税申告義務の有無はどのように判断する?
相続税は、不動産や金融資産、自動車などの相続した遺産に対してかかります。しかし、相続税は相続したすべての財産にかかるわけではなく、その財産から非課税とされるもの、特例で財産を減額、また税額の控除の制度がありこれらを差し引いたうえで最終的な相続税の金額が決定します。この記事では、相続税の申告義務の判断方法について解...
- インボイス制度が不動産賃貸オーナーへ与える影響と対応策について
この制度が始まったことによって、実は不動産オーナーにも大きな影響を及ぼすことになります。本稿では、インボイス制度が不動産賃貸オーナーに与える影響にはどのようなものがあるのか、そしてその対応策について解説していきます。インボイス制度が不動産賃貸オーナーに与える影響インボイス制度では、不動産賃貸オーナーがインボイス制...
- 【中小企業必見】悪化した資金繰りを改善するためにできることとは
資産を売却する手元の現金を増やす方法としては、手元の資産を現金に換えるという方法があります。企業として持っている不動産や、株式などの有価証券を売却することで、資産を現金化します。不動産などの場合、売却して現金化するまでに時間がかかるという問題はありますが、資金繰りを改善する方法としては有効な方法です。在庫を減らす...
- M&Aにおける合併の特徴と節税ポイントを解説
仮にグループ会社であったとしても、基本的に法人税の計算は会社ごとに行われます。そこで、利益を上げている会社と赤字を計上している会社が合併すれば、損益が一体となり利益が減るので、課税額が少なくなる可能性があります。ただし、合併によって資本金や従業員数が増えるため、法人税が増額になる場合もあり得ます。繰越欠損金の取り...
- 会社経営サポートで税理士に依頼できること
この方法を用いることでより早く納税額の見込みを計算することができ、その結果節税対策を早めに行うことができたりということが可能です。 〇会社の数字を見ることのできる税理士だからこそできること財務諸表をもとに会社の数字をしっかりと見ることのできる税理士は営業キャッシュフローがよくないので、営業のやり方を検討しましょう...
- 事業承継のメリット・デメリット
M&Aでの事業承継は財政基盤がしっかりしているところに事業承継を行うために、税金を支払えるかという心配をする必要がありません。しかし、従業員の処遇など引き継ぐ会社によって変わる可能性もあるため、注意が必要です。 佐藤昌哉税理士事務所は、名古屋市・北名古屋市・春日井市・東海市・瀬戸市を中心に、愛知県・岐阜県・三重県...
- 法人の年末調整の流れ
2、年末調整の計算まず、総支給額から、給与所得税額を引き、給与所得を算出します。そして、この給与所得から基礎控除や扶養控除といったその他の控除額を引き、所得額を算出します。この所得額が、所得税が課される金額となるため、この金額に税率を掛け、所得税額を計算します。そして、源泉所得税額との差額を計算し、徴収額の方が多...
- 年末調整とは
■所得税の計算方法まず、総支給額から、給与所得税額を引き、給与所得を算出します。そして、この給与所得から基礎控除や不要控除といったその他の控除額を引き、所得額を算出します。この所得額が、所得税が課される金額となるため、この金額に税率を掛け、所得税額を計算します。 佐藤昌哉税理士事務所は、名古屋市・北名古屋市・春日...
- 記帳指導を税理士に依頼する理由
どの部分の経費を抑え、どの事業の利益を伸ばすのか、どこに税金がかかっているのかなど、さまざまな判断の指標となります。 経理にミスがあれば、経営方針に影響したり、税務調査の対象になったりなど、経営に支障が生じることとなります。最悪の場合追加の支出が出ることになるため、ミスなく業務を遂行する必要があります。税理士に指...
- 副業の確定申告はいくらから?
確定申告はその年度にどれくらいの所得を得たのか、それに応じていくらの税金を納めなければならないのかを申告することをいいます。 確定申告を行わない場合、無申告加算税や延滞税を課税されることがあります。無申告加算税、延滞税はともに、確定申告書を3月15日までに提出しなかった場合、納付すべき本税に加えて課される罰金のよ...
- 個人事業主の法人化手続き
法人化とは、個人事業主が株式会社や合同会社などの法人を設立し、事業を法人に変更することを指します。法人化・法人成りには、節税効果などの様々なメリットがあります。近年、会社設立の際の最低資本金制限が撤廃されたこと、役員数の規制も緩和されたことを受け、多くの個人事業主様が法人化・法人成りを行い、そのメリットを享受して...
- 月次決算とは?目的や内容、メリット・デメリットなど
月次決算を行うことで毎月の損益を計算することが出来るので、仮に経営方針に変更があった場合にもすぐに変更することが可能です。 ・決算のミスをあらかじめ防ぐことが出来る月次決算を行うことで年次決算の際には見抜けない、もしくは見抜いたとしても修正が面倒になることを事前に防ぐことができるようになります。 その一方で、次の...
- 相続税の申告期限はいつまで?税理士に依頼するメリットも併せて解説
(1)延滞税など追加の税金がかかる場合期限内で申告を行わずに期限が過ぎた場合、利息に当たる延滞税や無申告加算税、重加算税などが課されます。単に申告をうっかり忘れてしまった場合では延滞税や無申告加算税のみが追加で課されますが、悪質であったり長期間に渡って納付を行わなかった場合には重加算税などが課され、非常に重い税金...
- 資金繰り表とキャッシュフロー計算書の違い|それぞれの活用法とは
◯資金繰り表、キャッシュフロー計算書とは、両者の違いは?資金繰り表とキャッシュフロー計算書はどちらも会社の資金やその流れに係る書類です。会社の資金の額やそのバランス、流れなどが判明し、融資や今後の経営判断において非常に重要な役割を果たします。これらを活用することで経営状況の判断につながったり、今後の資金の増減から...
- 税理士に税務調査の立会いを依頼する際の費用相場や事前準備など
万円前後、修正申告のための計算や手続きで10~20万円程度かかることが多いです。ただし、状況によって費用は変化しますので、税理士に確認しておきましょう。税務調査の立会いを依頼する際の事前準備税務調査が行われる際には、事前準備を行うことが必要です。従業員がいる場合、従業員にも協力を求めることになりますので、必ず事前...
- 【個人事業主の確定申告】領収書がない場合も経費にできるか
個人事業主が確定申告を行う際には、領収書を取りまとめ、確定申告の際にはその領収書をもとに経費の計算を行って申告をする必要があります。しかし、領収書をもらうことを忘れてしまった、領収書を紛失してしまったという場合には経費にできないのでしょうか。本稿では、領収書がない場合でも確定申告ができるかどうかについて解説してい...
- 【税理士が解説】法人が銀行融資の審査に通るためのポイント
本稿では、法人が銀行の融資審査に通るためのポイントについて解説していきます。銀行はどこを見ているのか銀行は融資を行う際にどのようなことを見ているのでしょうか。ひとことで表現するのであれば、「返済能力が確実にあるのかどうか」という点を見ています。 その判断は、決算書や事業計画書の内容など事業者が提出した資料から行う...
- 法人税の中間納付とは?いくらからが対象?
法人は事業年度であげた利益に対して、法人税を支払う必要があります。事業年度終了時から2か月以内に法人税の申告から納税までを行う必要がありますが、法人によっては確定申告時の納付とは別に「中間納付」を行う必要があります。本稿では、法人税の中間納付とはどのような制度なのか、そしてどのような法人が対象なのか解説していきま...
- 賃上げ促進税制とは?最新の改正ポイントをわかりやすく解説
人以下の法人もしくは個人事業主が対象となります。 要件税額控除率継続雇用者の給与支給額(対前年比)+3%以上10%+4%以上25%教育訓練費が対前年比+10%+5%女性活躍等支援+5% 給与支給額が4%以上7%未満の場合は、全企業向けよりも優遇を受けることができ、7%以上の場合は、全企業向けと同等の控除率になりま...
- 税務調査の流れ|実地調査では具体的にどんなことをする?
税務署の調査官が法人や個人事業主など申告した方を対象に、売上・経費・帳簿の記録が適正かどうかをチェックします。通常は事前通知がありますが、事前無予告調査が行われることもあります。税務調査の流れ税務調査の一般的な流れは以下の通りです。事前通知がある税務調査は、基本的に予告もなくいきなり始められるわけではありません。...
- 【税理士が解説】相続税が2割加算になるケースと対策を解説
割加算になる場合でも、対策次第で節税することが可能です。2割加算と対策について解説しました。2相続税のまとめただ、相続の計算は複雑で、実際に課税額を減らせるかどうかは簡単には判断できない場合が多いです。実際に対策を行う際には、当事務所までご相談ください。
Knowledge佐藤昌哉税理士事務所が提供する基礎知識
-
法人が不動産を売却し...
個人が不動産を売却した場合には、譲渡所得税が課税されます。一方、法人が不動産を売却した時には、他の所得と合算し […]

-
株式譲渡による事業承...
会社の事業承継を考えた場合、後継者に会社を承継させる方法として、大きく3つの方法が考えられます。今回は事業承継 […]

-
法人税の中間納付とは...
法人は事業年度であげた利益に対して、法人税を支払う必要があります。事業年度終了時から2か月以内に法人税の申告か […]

-
個人事業主の法人化手...
法人化とは、個人事業主が株式会社や合同会社などの法人を設立し、事業を法人に変更することを指します。法人化・法人 […]

-
経理業務の目的と流れ
経理業務は、会社の経営には欠かせないものです。経理の目的と流れを知ることで、経理データを有効活用することができ […]

-
年末調整とは
■年末調整とは年末調整とは、会社から支給される従業員の給与の所得税額と、控除した所得税額を比較することで、過不 […]

Keywordよく検索されるキーワード
-
- 記帳代行 税理士 相談 春日井市
- 節税対策 税理士 相談 三重県
- 銀行対策 税理士 相談 岐阜県
- 節税対策 税理士 相談 東海市
- 銀行対策 税理士 相談 三重県
- 銀行対策 税理士 相談 名古屋市
- 記帳代行 税理士 相談 名古屋市
- 事業承継 税理士 相談 三重県
- 税務調査 税理士 相談 瀬戸市
- 税務相談 税理士 愛知県
- 銀行対策 税理士 相談 瀬戸市
- 経営計画 税理士 相談 瀬戸市
- 節税対策 税理士 相談 春日井市
- 税務相談 税理士 岐阜県
- 資金繰り 税理士 相談 愛知県
- 税務相談 税理士 瀬戸市
- 事業承継 税理士 相談 春日井市
- 税務調査 税理士 相談 三重県
- 節税対策 税理士 相談 瀬戸市
- 経営計画 税理士 相談 東海市
Tax accountant税理士紹介

「わからないことをわかりやすく、どんなご相談も懇切丁寧に」。
税務・経理・会計業務を中心に市民の皆様のお困りごとに対応。ご相談が速やかな問題解決へと繋がりますようお手伝いいたします。
所属団体名古屋税理士会
税理士佐藤昌哉(さとう まさや)
-
- 所属団体
-
名古屋税理士会名古屋東支部(118216)
認定経営革新等支援機関
-
- 経歴
- 理系の大学を卒業後、法律事務所に勤務。資格の取得に興味を持つ。平成22年、税理士試験5科目(簿記論、財務諸表論、所得税、消費税、相続税)合格。平成23年4月21日税理士登録。その後、独立し、佐藤昌哉税理士事務所を設立・開業する。
-
- 対応エリア
- 愛知県・三重県・岐阜県
-
- 注力分野
- 企業財務と顧問税理士検索サポート、相続税・贈与税相談サポート
Office事務所概要
| 事務所名 | 佐藤昌哉税理士事務所 |
|---|---|
| 所在地 | 〒461-0011 愛知県 名古屋市東区白壁1丁目23番地 |
| 電話番号 | 052-951-3959 |
| 受付対応時間 |
09:00~17:00(土日除く) |
| 相談料 | 初回相談無料/初回電話相談無料 |